四柱推命を学んでいくうちに、倒食(とうしょく)という言葉にぶち当たります。
ざっくりいうと衣食住の神と言われている食神が剋されるという意味です。
初めて聞いた時は、ドキっとして食神が倒されるということは、「福が逃げるとか?」「良くないことが起きるのか?」とこれまた、思考が暴走してました。
倒食は、偏印から剋される関係で、私はこの倒食を命式の中に持っています。
「食神」と「偏印」どちらも強くて、どちらも私の一部なのですがこの両方のバランスが崩れると、どうなるのか?
楽しいことが好きな食神と知識と理屈の偏印が合わせると、「楽しみたいのに理屈で止めてしまう」「感じたいのについ分析してしまう」といったことがよく起こります。
そんな心の逆流をよく経験してきました。
今回は、倒食を命式に持つ人間として、その意味や仕組みと年運ででた時の体感を、私なりに解説していきます。
倒食とは?四柱推命での意味としくみ
四柱推命では、倒食(とうしょく)=食神が偏印に制される状態のことです。
五行で見た関係
- 食神⇨自分(自星)が生み出す五行(漏気)「楽しみ・表現・創造性」
- 偏印⇨自分(自星)を生み出す五行(生気)「直感・ひらめき・知識・内省」
本来は「印星→日主→食神」というスムーズな流れ(生→我→泄)になるのが理想です。
しかし偏印が強くなりすぎると、偏印が暴走して食神をストレートに抑えてしまいます。
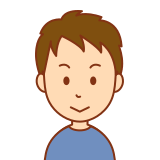
自分の中で口うるさい母と遊びたい子供が同座してる感覚ですかね笑
命式上で倒食になる条件
※命式全体を観なければわかりませんが、
以下のような場合は、倒食の性質が強く出るとされています。
- 命式内に偏印と食神が同時にある(特に隣り合う場合)
→ 「偏印+食神」しかない命式は典型。 - 偏印が強く、食神が弱い(比率のバランス)
→ 偏印が複数、または大運・年運で偏印が巡る時。 - 食神の五行が偏印に剋される五行関係にある
→ 例:木(偏印)が土(食神)を剋すなど。 - 印星が用神ではなく忌神として働いている場合
→ 印が過剰だと、思考過多・分析過多・理屈っぽさとして現れる。
→命式に財星があれば、偏印を剋すので傾向はマイルドになる。
命式に倒食を持つ私が感じる傾向
食神も偏印もどちらも私の一部で大切なのですが、バランスを崩すと心の逆流のような感覚が起こります。
そして、命式においては柱ごとに年齢で区切られてます。
「楽しむこと」に罪悪感を持ってしまう時期
倒食を感じてきたのは、月柱の年齢(20歳〜30後半)に入ったあたりでした。
20代後半〜でしょうか?本来はもっと早いみたいですが、個人差があります。
それまでは、食神を謳歌しまくりで考えずにやりたいことに飛び込む人間でした。
しかし月柱の年齢に差し掛かると、社会や仕事の忙しさや責任が増えていき命式のバランスや大運の相性によって色がはっきりと出るようになります。
年柱と日柱の食神で生きてきた感覚で、自由に楽しむ力はあるものの、月柱の偏印に差し掛かりなおかつ大運に偏官が巡ることで、「どこかでちゃんとしなきゃ」「真面目にやらなきゃ」と自分をいつしか縛り目を張るようになりました。
そして、無意識に「好きなことを優先することはわがまま」と思って生きてるようになりました。
つまり食神が社会ルールに抑えられて、いよいよ倒食の気配が生まれる段階に入ったのです。
年齢によって変化する倒食の出方
私の例により、柱ごとによって年齢が決まってます。
倒食の傾向は、年齢やそのとき巡っている星によっても少しずつ変化します。
私の場合、年柱が食神(月柱が元命共に偏印)なので、「感じる→考える→統合する」という流れが人生のテーマのように続いています。
- 0〜20代前半:食神の時期(年柱)
→ 感覚で動く、自由で自然体。野生児と呼ばれていた、あだ名は「猿の子」
→ でも社会とのズレで「抑える」「我慢する」ことを学ぶ。 - 20後半〜40代:偏印の時期(月柱)※元命偏印
→ なんでも意味づけて考えたくなる。口癖は「なんで?」「どうして?」
→ 「感じたいのに考えてしまう」状態=倒食の本格期開始。 - 40代以降:統合のはじまり(日柱食神・時柱偏印)
→ 理解と感性がつながって、表現が成熟していくと予想。まだここはどうなるか検証中。
このように、どの年齢に何の星があるか?また大運の流れによっても倒食の出方も変わります。
私の場合は交互に鍛えられながら、大運にも揉まれ自分の表現を再構築していくためのサイクルの最中なのだと感じました。

命式に倒食がある方、どう使いこなしてますか〜?
知りすぎて疲れる、考えすぎて動けない
完全に偏印に命式を乗っ取られた時期は(20代後半〜)、「情報」「意味」「理由」を求めすぎて疲れていました。
でも、この時期に四柱推命に出会って勉強したいと思えたし、何より自分の人生を追求し意味を知りたかった。
偏印が主導する時期は、「情報」「意味」「理由」に追われて内の世界にこもるような時です。
偏印は、ひらめきや直感的でもありますが行動に起こすかは別です。
ひらめいたことに対するリスクを探しまくる傾向にあり、行動するかどうかは自星にかかってます。
感性が鈍るように感じますが、実は内側を整えるプロセスに移行している最中だと知ることになります。
倒食のについてや自星の使い方について、下記事にも載せてます⇩
年運で倒食が巡るときに起こる変化
年運で偏印や食神が巡ると、普段よりも 感じる力(食神)と考える力(偏印) が強く刺激されます。
倒食の年になる条件はシンプルで、命式に食神か偏印があり、反対側の星(食神 or 偏印)が年運・大運で来ること。
これだけで、心の流れが一度内側へ向かい始めます。
ただし同じ「大運に食神が来た」ケースでも、出方は命式バランスによって大きく違うことが分かっています。
ここからが本題です。
倒食の年は全員が同じように揺れるわけじゃない
最近、実例を2つ見て強く感じたことがあります。
どちらも元命が偏印+大運に食神。
一見、同じ倒食の年に見えるのに、出方が正反対でした。
【実例①】大運に食神が来て、明るく外向きになれた人
- 年柱:財星
- 日柱:食神
この人は、月柱は印綬と元命は偏印です。
食神が大運で強まり、元々もっていた社交性(財星)と楽しむ力(食神)が一緒に動いた。
→ その結果
- ワイワイ賑やかにできる
- 人の輪に入れる
- 食神の陽気さが素直に出た
- 偏印の深さが良い方に活かされる
大運の食神が、命式のポジティブな部分を拡張したパターン。
【実例②】大運に食神が来ても、内側にこもってしまった人
- 年柱:比肩
- 日柱:比肩
こちらは同じく月柱に印綬と元命偏印+大運食神なのに、外向きどころかより深く内側にこもる形になったパターンです。
理由は明確で、
命式の柱に外へ向かう星(財・官)がなく、自星ばかりだったから。
→ こうなると
- 食神が来ても外に出せない
- 偏印が自分を守ろうとしてブレーキをかける
- 食神の“ゆるみ”が怖くなる
- 動くより、引きこもりが強くなる
つまり、同じ食神大運でも命式が外向きか内向きかで反応が真逆になる。
ここから言えることは、「食神の大運=楽しい時期」とは限らないということです。
外向きの星(財・官・食神)が命式にある人は
→ 食神が巡ると、気楽さ・楽しさが表に出やすい。
自星や印星が強い人は
→ 食神が巡ると、緩みが不安になり、むしろ内側へ戻る。
倒食は反応の差が大きい星なので、命式の全体バランスが出方を決めるんだと実例から確信しました。

だからこそ、倒食の年は自分の命式をどう活かすかが鍵になります。
まとめ
倒食があるからといって悪い命式というわけではありません。
内側を知りながら、食神の楽しさも偏印の繊細さも、どちらも否定せずに使いこなす。
そのバランスを学ぶ時間が、倒食が巡る時期の本当の意味なのかもしれません。
お読みいただきありがとうございました。

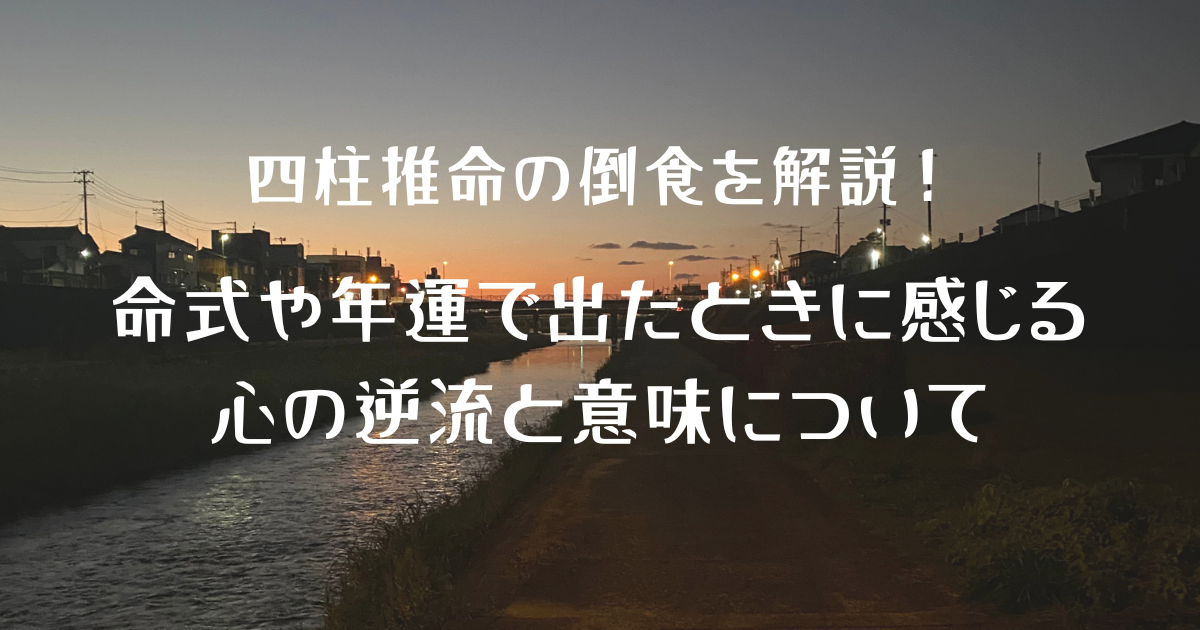



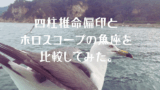





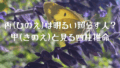
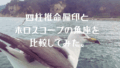
人気記事